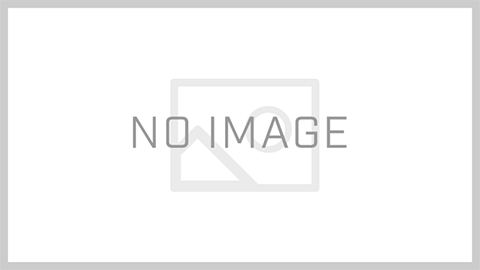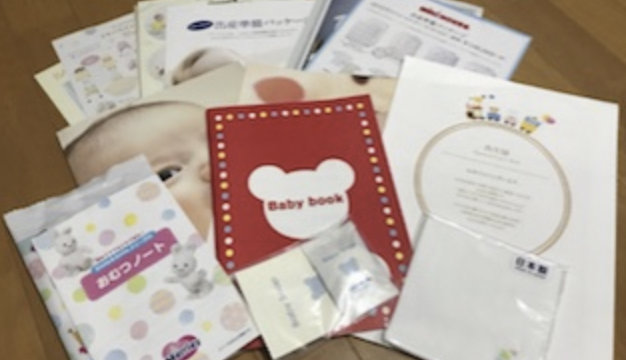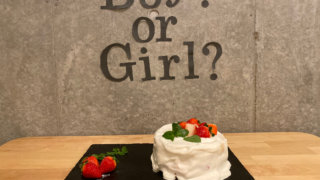こんにちは!
”EduLaboJapan”代表のささおらんです。
1歳をすぎてくる頃に、歩けるようになり「ひとりでやりたい!」という気持ちが強くなってきます。
この気持ちが自立への第一歩です!
今回は「ひとりでやりたい」という気持ちを尊重し、ひとりでできる着替え環境の整え方についてご紹介します!
もくじ
【モンテッソーリ流】キッズクローゼットの整え方
子どもサイズのものを用意しよう!

クローゼットを準備する時に一番大切なのは「ひとりでできる」という環境。
その為、子どもの手が届かない大人が使うような高さのあるタンスだったり、引き出しがかたくてあけられなかったりという障害がないように準備しましょう。
子どもの手の届く大きさ、子どもが扱いやすい引き出し、かつ安全なものを準備してあげましょう。
洋服の数は少なくする!

洋服をもっている分だけ収納すると、子どもにとっては選択肢が多すぎてしまい、「選ぶ」より「遊ぶ」方にシフトしてしまうことが多いです。
はじめはトップス2・ボトムス2・下着2…というように2択にしてあげましょう(子ども発達段階によって選択肢を増やしてあげても大丈夫です)。
お着替えをイヤイヤしちゃう子どもも「選ぶ」というプロセスを通るとすんなりお着替えモードに切り替わることも多いです。
試してみてくださいね。
また、「選ぶ」というプロセスはモンテッソーリ教育で大切にしていますので、1つずつ用意するのは避けましょう。
【モンテッソーリ流】着替えの環境の整え方
脱ぎ着しやすいデザインのものを用意する
※上記の動画は娘が1歳4~5ヶ月頃の着替えの様子
「ひとりでできた!」という気持ちを感じることがとても大切です。
なるべく大人の手を借りずにお着替えができるように、ファスナーがないゴムのものだったり、ボタンのないものだったり、着脱が簡単にできる洋服を用意してあげましょう。
ボタンやファスナーなどは、別で教材や活動の場を用意してあげて、できるようになってから洋服にも取り入れるようにしてあげましょう。
洋服の前後がわかるようにする
せっかく自分で着替えができたのに、「後ろ前反対よ」と言われやり直しされたら、子どものやる気も一気にダウンしてしまいます。
そこで洋服の前後がわかるように印をつけてあげましょう。
靴下などは、足の甲にキャラクターなどが描かれているものがおすすめ。
(我が家の例)
「おさるのジョージが見えるように履こうね」と言葉かけをすると、自分で「ジョージみえない」と履き直して、自己訂正することができています。
視覚的にわかると自分で意識しながら着ることができるようになるので、大人にとっては少し手間ですが、ぜひ準備してあげてくださいね。
クローゼットの近くに椅子(スツール)を設置する

歩き始めた子どもたちにとって、着替えは難しいもの。
そこでクローゼットの近くにスツールを設置しましょう。
スツールに腰をかけるとボトムスなどの着脱もしやすくなります。
うちでは下記のベビービョルンのステップを使用しています▼
ベビービョルン ステップ(1個)【ベビービョルン(BABY BJORN)】[トイレ お風呂 ケアグッズ トイレ用品]楽天で購入
スツールを用意するのが難しいようであれば、100均などで購入できる発砲スチールのブロックなどでも代用ができます。

鏡を置いてチェックできるようにする

できればクローゼットの近くに鏡を設置してあげましょう。
洋服が前後していたり、シャツが見えてしまったりしているときに、自分で気づける環境を作ってあげましょう。
大人も「ズボンの履き方が違うよ」と直接指摘するのではなく、「鏡で確認してごらん」と言葉をかけるようにしましょう。
こういう風に習慣付けてあげることで、身だしなみを整え、自分の外見に気を配れるようになっていきます。
さいごに

子どもがひとりでやろうとする姿は大人にとっては非常にもどかしく、口を出したり手を出したりしたくなってしまいます。
でも子どもは大人が思っているよりもできることが多く、また「自分でやりたい!」という気持ちを強くもっています。
まずは子どもが自分でやり始めたら口や手を出したい気持ちをぐっと堪えて見守ってあげてください。
まず子どもがひとりでやってみて、できない時に手伝って良いか確認した上で、「こうしてやるんだよ」とやり方を見せてあげたり、「手伝ってだね」と困った時に言ってほしい言葉を添えながら、サポートをしてあげてくださいね。
こちらもおすすめ▼
【おうちでモンテッソーリ教育】子どもを片付け上手にするおうちの環境づくりと関わり方のコツを大公開!